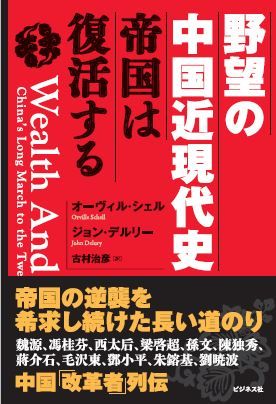2021年12月3日に副島隆彦著『ディープ・ステイトとの血みどろの戦いを勝ち抜く中国』(ビジネス社)が発売される。副島先生の中国研究は既に10冊を超えた。私も2019年に副島先生のお供で深圳と香港を訪問した。その時の様子はこのブログでもご紹介した。
※『全体主義中国がアメリカを打ち倒す』(副島隆彦著)発刊記念中国訪問記(1):深圳編
※『全体主義中国がアメリカを打ち倒す』(副島隆彦著)発刊記念中国訪問記(2):香港編
『ディープ・ステイトとの血みどろの戦いを勝ち抜く中国』では、中国最高指導部が、「災い転じて福となす」戦略で達成した成果7つについて書いている。その7つについては、「はじめに」から以下のように引用する。
(貼り付けはじめ)
(1) 「デジタル人民元」がアメリカのドル覇権を叩き潰しつつある。デジタル人民元 が 世界通貨体制の 要(かなめ)となるだろう。
(2) 台独[たいどく](台湾独立派)を叩き潰して、アメリカが台湾に肩入れし、手出し干渉することを撃退する。日本やオーストラリアごときは、その手駒(てごま。paw ポウ)に過ぎない。
(3) 習近平は、勉強させ過ぎ(過酷な受験勉強)の子供たちを救出した。精鋭(せいえい)国際教育集団(OSIEG)という巨大教育産業(全国学習塾チェーン)を叩き潰して倒産させた。ニューヨーク上場株式消滅。ゲーム・アニメ・動画も同じく弾圧した。
(4) 経営危機の「恒大(こうだい)集団」を始め最大手不動産デベロッパーを、うまく国家の住宅政策に取り込んだ。恒大は同業種の国有企業が吸収合併(マージャー ・アンド ・アクイジジョン)。過熱した住宅価格も2割下げる。そしてゆくゆくは、14億人の全ての民衆(国民)に床面積100㎡(30坪)の高層住宅を持たせる(買えるようにする)。
(5) ”中国版ビッグテック” (アリババ、テンセントなど)を、デジタル人民元の仕組みの中に解体的に取り込む。
(6) 9月24日に、ビットコインと全ての仮想 通貨(かそうつうか。暗号資産 クリプト・アセット)を最終的に禁圧し、国外追放にした。鉱山(マイナー)主たちの多くがアメリカのテキサス州に逃げた。仮想通貨はやがて叩き潰され、世界通貨体制の中にブロックチェーン技術を中心にして取り込まれる。 新しい世界通貨体制(ニュー・ワールド・カレンシー・オーダー)は予定通り、やがて、中央アジアのカザフスタン国に、すべての国の政府と中央銀行が集まって、国際条約で発足する。
(7) 生物兵器(バイオウエポン。細菌爆弾、ジャームボム)としてのコロナウイルスの武漢への攻撃を、中国は完全に撃退した(2020年9月に習近平が勝利宣言をした)。中国はディープ・ ステイト(陰[かげ]に隠れた世界支配者ども)の中国攻撃を、内部に攻め込ませる形で迎撃(げいげき)して粉砕した。中国の勝利だ。 このあとのm(メッセンジャー)RNAワクチンという世界民衆大量殺戮(さつりく)の邪悪な生物化学兵器も中国は見抜いて防御した。愚か者の日本や欧米の白人たちは、これから国民がたくさん死ぬ。(1-4ページ)
(貼り付け終わり)
重要なのは、中国国内に分裂や分断をもたらさないことである。そのために習近平政権は、「共同富裕」という考えで、中間層を増大させ、いまだに貧しい6億の農民の報酬を引き上げることを宣言した。分厚い中間層はどの国にとっても安定と発展のためには不可欠な要素である。そのために急激な高度経済成長でもたらされた格差を是正する。
更に言えば、一時期の日本よりも厳しい受験戦争から子どもたちを解放すること、そして、スマートフォンやSNS、ゲームへの依存から救出することを目指している。この点が重要だ。なぜならば、若者たちのスマートフォンやSNS、ゲームへの依存は、すでに先進諸国でも問題になっているからだ。これらは孤立感や憎悪を増幅させる。その結果として、社会は壊れていく。私は、2021年11月25日に『ビッグテック5社を解体せよ』(ジョシュ・ホウリー著、古村治彦訳、徳間書店)を出版したが、そこにも同様のことが書かれている。現在、世界各国が抱える問題は共通しており、それは深刻なものとなっている。中国も例外ではない。そして、中国最高指導はそれらの諸問題を逆手(さかて)にとって、「禍を転じて福と為す」ということで、より良い状態を生み出そうとしている。
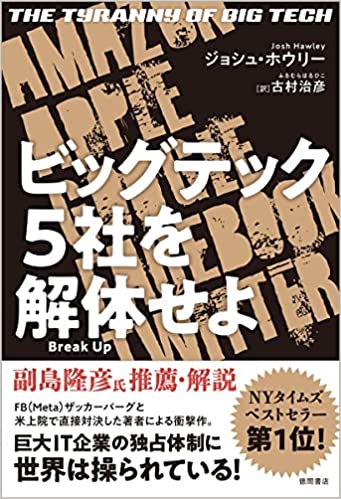
ビッグテック5社を解体せよ
ここでちょっと宣伝をさせていただくと、私は2014年に『野望の中国近現代史』(オーヴィル・シェル、ジョン・デルリー著、ビジネス社)という翻訳本を出版した。 この本は非常に重要な本だ。本ブログ2021年7月9日付記事「「恥辱の世紀」から「復興」へ「歴史のバトン」をつなぐ中国:「富と力」を求めた200年間」で、2021年7月1日付でアメリカの外交専門誌『フォーリン・ポリシー』誌に掲載された「中国共産党はこれまで常にナショナリスト政党であった(The Chinese Communist Party Has Always Been Nationalist)」(ラッシュ・ドシ筆)という記事を紹介した。
※「恥辱の世紀」から「復興」へ「歴史のバトン」をつなぐ中国:「富と力」を求めた200年間
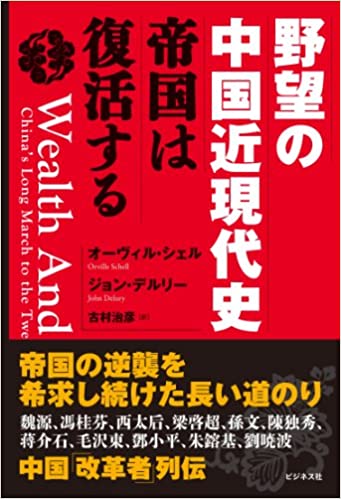
この記事は『野望の中国近現代史』の内容をそのまま要約したものだった。現在はほぼ絶版状態になっており、新刊本は書店では手に入らないし(アマゾンでは残り1点だそうだ)、電子書籍版もないので、中古本を買っていただくしかないが、中国の近現代史を大づかみに一気に理解したい方には最良の一冊である(少し分厚いですが。私の高校の同級生は2度読んだよと言ってくれました)。アメリカの知識人階級の中国近現代史理解は本書でできていると言っても良いだろう。
最後に私の中国体験を書いておきたい。2019年に中国を訪問したが、それ以前にも行ったことがある。私は1984年、当時小学4年生だったと記憶しているが、地元鹿児島の南日本新聞社主催の「子ども遣唐使」という小中学生だけの中国訪問ツアーに参加した。これは、鹿児島の薩摩半島の南端にある坊津(ぼうのつ)という場所に、奈良の唐招提寺の開山となった鑑真和上(がんじんわじょう)が漂着した歴史があること、当時は日本からの中国への渡航も制限が緩和されたこともあっての子どもたちの訪問団が実現したということだったと思う。前年が第1回で、それに参加した子どもの保護者から話を聞いた親が勧めてくれたという記憶がある。私にとっては当然ながら初めての海外旅行だった。その頃の鹿児島で海外旅行に行く小学生なんてほぼいなかった。
私たちは鹿児島空港から長崎空港へ飛び、長崎空港から中華民航機で上海に向かった。私たちの訪問地は上海と無錫だった。上海空港はただただ広かったが、飛行機が到着した場所から空港の建物まで歩いた。私はそれまで子供ながらに鹿児島空港と羽田空港を利用した経験があったので、雑草が生えている滑走路を歩きながら、「タラップもないなんてなんてみすぼらしい」という感想を持った。中国側からは通訳の方もついて、ホテルに着き、翌日からは観光や少年宮と呼ばれる教育施設の訪問などがあった。
私が記憶しているのはパンダだ。やっぱり子供である。私は親戚もいた関係で東京には毎年のように行っていたので(こんな子供もまた鹿児島では珍しかった)、日本の上野動物園でパンダを見た経験はあった。上野にいたパンダは空調の聞いた檻(というよりも部屋)に入っていて快適そうだった。一方、上海動物園のパンダ。上海のパンダはただの檻に入れられて、夏の猛暑の中、水風呂にひたすら入っていた。そして、夏バテのためか昼寝をしていた。そこに、白人の親子もおり、子どもたちがパンダを起こそうとして「ヘイ、パンダ」「ヘイ、パンダ」と呼び掛けていた。「英語でもパンダはパンダって言うんだな」という妙な感心をしたことを覚えている。
上海の動物園には中国人の子どもたちもたくさん来ていたが、皆一様にランニングシャツに短パンだった。そこに外国語を話すこざっぱりとした格好の子供たちの一団がやって来たのが異様だったのか、私たちの後ろを同年代の子供たちがついてきた。私は子供心に、「日本が戦争をして負けた後の写真やドラマ、ドラマでよく見る格好だ」と思い、中国は貧しいんだと実感した。それから40年ほど経った訳だが、その時一瞬邂逅した、日本の子どもたちと上海の子どもたちは今や中年になっている訳だが、その生活はどうなのだろうかと考えると、大きな逆転があったのではないかと容易に推測できる。彼らは中国の高度経済成長を経験し、私たちは失われた30年を経験した。
それから由緒のあるお寺を訪問した。その中身については全く覚えていないが、私は壁に何か描かれていたが乱暴に消された跡があることに気付いた。それが歴史のあるお寺にそぐわないと子供心に思ったのだろう、通訳の方に「あそこだけどうしてあんなに汚れているんですか」と質問した。通訳の方は「文化大革命というものの跡です」と教えてくれた。私は「文化大革命とは何ですか」と質問した。その答えは「日本に帰ってお父さんとお母さんに聞いてください」というものだった。それでこの話は終わり、あまり良くないことなのだろうと察することができた。それから、この通訳の方は何かと私に気遣いをしてくれるようになった。どこかに行くたびに私の感想を聞きたがり、面白そうに聞いてくれた。他の子どもたちはちょっと違うと思ってくれたようだ。
後日談では、私が入学した高校の美術室にはベランダがあり、そこは高校生たちが隠れてタバコを吸うスペースになっていた(今はそうではないと思います)。私はそこの掃除当番になって毎日吸殻を捨てていたのだが、ある日壁にうっすらと「造反有理」と書かれているのを見つけた。これは文化大革命のスローガンだと知っていたので、恐らく学生運動の名残なんだろうと納得した。その後、その高校の出身者である私の叔父に話をしたら、「懐かしいなぁ、それを書いたのは私だよ」と教えられて、小学4年生で知った文化大革命という言葉が非常に身近に感じられた。
1984年はロサンゼルスでオリンピックが開催された年だ。ご多分に漏れず、私もオリンピックを楽しみにしており、コカ・コーラを何本か飲むと貰えた(というシステムだったと思う)、マスコットのイーグル・サムの付いたグラスを集めていた。中国訪問中はオリンピックの開催期間でもあったので、ホテルのテレビでオリンピックを見ることになったが、当然のことながら、中国での放送は中国選手ばかりが映る。今ではそんなことは何とも思わないが、当時子どもだった私は日本選手の活躍が見たかったので大いに不満だった。 ホテルでテレビを見ていた時に、日本のドラマの吹き替えが多かったのも印象的だった。「赤いシリーズ」と呼ばれたドラマで、山口百恵が出ているシリーズが丁度放送されていた。「わぁ、山口百恵だ、懐かしいなぁ」と思ったことを覚えている(山口百恵は私がもっと小さい頃に既に引退していたので)。また、上海のバンドのあたりには、三田佳子がキャラクターの三洋電機の洗濯機の大きな広告があったことを覚えている。
中国訪問中、私は誕生日を迎えた。ホテルでは心づくしのケーキを出してくれた。しかし、このケーキはスポンジがパサパサ、クリームも日本のものとは違う感じで、子どもたちの口には合わなかった。また、ある時に通訳の方と話していて、自転車が給料1カ月分だと教えてくれて、その給料は日本円で言えば8000円くらいと教えてもらえた(通訳の方の給料はもっと高かったと思う)。私の親は教師をしていたが、それよりもずっと高い給料をもらっている(それでも日本では真ん中くらい)ということを知っていたので、中国の貧しさを実感した。
私が子どもの頃に中国を訪問して40年、中国は日本を逆転した。これからその差は広がっていくだろう。一人当たりのGDPはまだ日本が上回っているが、それもいつまで続くか分からない。日本の衰退・縮小が続き、中国が成長を続けていけば、自然とそうなる。既に中国の都市部では生活水準で日本を上回っているところが出ている。中国が本気で中間層の厚みを増そうとして、配分や再配分に本腰を入れていけば、生活水準は上がっていく。ランニングシャツに短パンだった上海の子どもたちは今や一流ブランドの洋服に身を包み、あの頃こざっぱりとした格好をしていた私たちはどうだろうか、ユニクロの洋服を着て満足している。この大きな逆転を実感することは歴史の大きな流れを実感することだと私は思う。副島先生の中国研究本を読みながら、なぜか昔話を書きたくなった。長くなってしまって申し訳ありません。ご寛恕の程、お願いいたします。 (貼り付け終わり) (終わり)
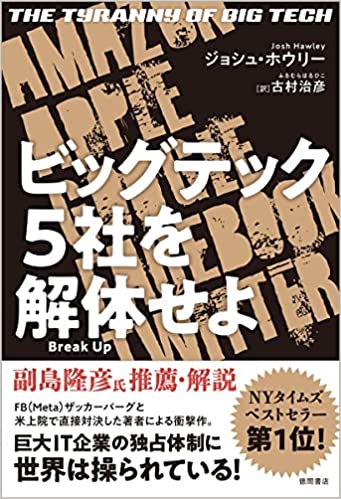
ビッグテック5社を解体せよ