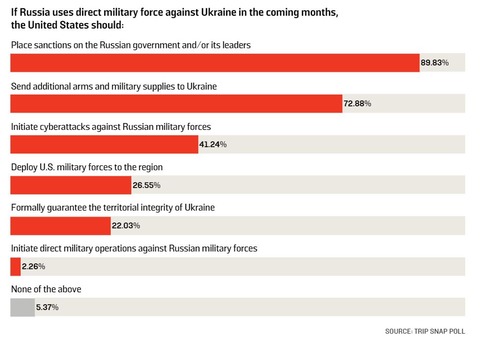古村治彦です。
今回は少し難しい話になる。と言っても、「そんなことは当たり前ではないか」ということでもある。そして、「学者たちは物事をどんどん細かくしていって、かえって物事が見えなくなり、大きな理解ができなくなっているんだ」ということが分かってもらえる話になると思う。
政治学という学問は大きなくくりであり、その中に様々な学問分野がある。方法論、比較政治、政治思想、日本政治やアメリカ政治など一国の国内政治、国際関係論といった分野が存在する。そして、それぞれの中でまた細分化がなされている。政治学の教授もしくは研究者というのは政治学全体の大隊の知識は持っているが、当然のことながら自分の専門を深く研究することになる。そうなると、たこつぼ的な状況が出てきてしまうのは仕方がない。医学を例にして考えてみても、内科から外科、泌尿器科、産婦人科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科などなど多岐にわたる。それぞれを全て極めた医師は存在しなのではないかと思う。
政治学に統合されたアプローチが必要という議論がある。これは理解できることであるが、これは非常に難しいことだ。政治学を含む社会科学の目的とは、社会で起きる様々な現象を分析し説明することから最終的には法則の発見であるが、これは大変に難しい。法則とは全ての環境で機能するもので、これが分かれば「予測」ができるということになるが、人間が絡む社会においてはそのような予測は難しい。統合されたアプローチは今のところ不可能である。
ただ、政治という人間の営為ということになればそうも言ってはいられない。国家を運営する、政策を立案し、実行するということになれば、諸理論に経験や知識をプラスして、「大戦略」を作らねばならない。専門家のような狭く深い見方ではなく、深さは少なくても広さは気宇壮大なものであるべきだ。
アメリカの外交政策や安全保障政策分野で考えてみると、弁護士や外交官として経験を積み、もしくは研究者として研究をしながら、抜擢されて国務次官補代理や国防次官補代理になって外交や安全保障の分野で経験と専門性を高め、評価を高めていくパターンが多い。そうした中で、専門性と知識と経験を高め、より多くの材料や要素を取り入れながら、また時には多くの材料を取捨選択しながら、政策を立案し、政策判断を下すということになる。
日本に「大戦略」があるだろうか? 残念ながら見当たらない。場当たり的でかつアメリカの言いなりになっておけばよいということが大戦略の代わりになっている。しかし、それではアメリカの衰退が進む中で、羅針盤がない中で公開をする船と同じになってしまう。つまり、どこの港にも着けないということになる。
(貼り付けはじめ)
大戦略は十分に壮大ではない(Grand Strategy Isn’t Grand
Enough)
―世界最高の国家安全保障の専門家たちは、外交政策のあらゆる側面を研究することを知っている。しかし、それだけでは十分ではない。
アラスディア・ロバーツ筆
2018年2月20日
『フォーリン・ポリシー』誌
http://foreignpolicy.com/2018/02/20/grand-strategy-isnt-grand-enough/?utm_content=bufferf8a38&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
大戦略(Grand Strategy)は、外交政策と国家安全保障の専門家たちにとってよく知られている概念だ。大戦略の意味は長年にわたり膨張してきた。専門家の中には、肥大化しすぎてもはや役に立たないと考える人もいる。しかし、それは間違いである。大戦略の本当の問題は、それが十分に壮大でない(not grand enough)ということだ。
19世紀、大戦略とは実際に戦争をすることであった。一つの作戦地域にいる司令官は、敵を倒すための戦略を持っており、最高司令官は、多くの作戦地域に軍隊を展開するための大規模な計画を持っていた。ある文筆家は、1904年に、大戦略とは「陸上と水上にある国家の全武力」のことだと説明した。
総力戦の到来で、その概念は拡大した。エーリッヒ・ルーデンドルフ元帥が主張したように、戦争の勝利が国家の物理的、精神的な力の総動員に依存するならば、戦時計画も同様の大規模な範囲を持つべきであると考えたのである。B・H・リデル・ハートは、大戦略を「社会・経済活動のあらゆる側面を戦争目的の達成に向けて指導する国家政策」と定義した。他の専門家も1942年に、「大戦略の基本は戦争と戦争が起こる社会との相互関係である」
ということに同意している。
冷戦が始まると、その概念は再び拡大した。大戦略は、依然として社会のあらゆる資源を動員することに関係していた。しかし、その目的はより曖昧になった。2度の世界大戦期間中、各国首脳は実際の戦争に関心を寄せていた。対照的に、第二次世界大戦後、各大国は数十年にわたる地位の優位をめぐる争いに巻き込まれた。このように、今日の大戦略は、トーマス・クリステンセンが定義するように、平時においても戦時においても「力と国家の安全を高めるために設計された国内および国際政策のフルパッケージ」である。
大戦略の理論化は、実際の意思決定のあり方とほとんど関係がない、と批判する人々もいる。現実の世界では、国内政策と国際政策の適切な調整はほぼ不可能であるという議論もある。指導者たちは先見性を備えていないし、明確に定義された目標に向かって安定したコースを維持することはない。むしろ、現状維持(status quo)を変化させ、実験をし、危機から危機へ移らせることが多い。
このような批判は、ほとんど見当違いである。漸進主義(incrementalism)や実験主義(experimentalism)は、不確実性(uncertainty)や政治的党派性(political polarization)がある状況では、多くは妥当な反応ということになる。更に重要なのは、実際の政策の方向性が不規則であったり、効果がなかったりするからといって、指導者たちが戦略を軽視していることにはならないことである。戦略的に振る舞おうとしても、それがあまり得意でない指導者もいる。しかし、下手な作家がやはり作家であるように、無能な戦略家もやはり戦略家である。また、どんなに綿密な計画を立てていても、出来事によって混乱に陥ることがある。
指導者たちは状況に応じて戦略を立てなければならない。世界は激動する危険な場所であり、指導者たちは重要な利益を損なわないようにするために、外交領域を無視することはできない。指導者たちは外交に携わらなければならない。それぞれの決断は、目的と手段、そして他の決断への影響について、何らかの計算(some calculation)によってなされなければならない。これらは、大戦略の基本である。専門家は戦略の質を高めようとするが、指導者たちが戦略的に行動しようとする衝動は既に存在している。
しかし、ここに難しさがある。国内政治の世界もまた同様に裏切りの世界だ。現実主義の大御所マキャベリは、君主は二つの恐怖を持たねばならないと警告した。「一つは臣下に由来する内なる恐怖、もう一つは外国の権力に由来する外なる恐怖」である。民主政治体制国家では、内政に不手際を起こした指導者たちは次の選挙で放り出される。独裁国家では、クーデター(coups)で倒される。また、不器用な指導者は、突然、国家が崩壊していることに気がつくこともある。外交の危機が指導者たちを戦略に向かわせるのなら、内政もまたその通りである。
これは容易に想像がつく。指導者たちは、秩序、繁栄、正義、そして自らの任期中の生存といった、国内の重要な利益に対する脅威を管理するための政治プログラムを常に洗練させている。彼らは、これらの利益を確保するために、社会的資源を動員し、政策手段を調整しようとする。言い換えれば、彼らは国内大戦略(domestic grand strategy)を策定する。指導者の中には、これをうまくこなす者もいるが、全ての指導者が大戦略策定を行うよう駆り立てられる。
これら2つの大戦略、外交分野の大戦略と国内分野の大戦略は、相互に密接に関係している。国内の平穏(tranquility at home)は経済成長に依存しており、国家の指導者たちは資源と市場を海外に求める。国内世論が揺れ動く中で、対外戦争は開始され、もしくは中止される。選挙権の拡大、福祉国家の建設、公民権の保護など、指導者たちは国内で譲歩を行い、海外でのキャンペーンへの支持を高める。主要な同盟諸国との貿易協定を強化するために、国内の規制権限が削減されるなどなどが行われる。この2つの大戦略の絡まり方のスタイルは無限大に存在する。
しかしながら、ここで私たちは概念的な問題に直面する。もし、外交と国内の二つの大戦略があるとすれば、どちらか一方が本当の大戦略ということになるのだろうか。また、指導者たちは本当にこのように考えているのだろうか。私たちはこれらの問いに対する答えを知っている。指導者たちはマキアヴェッリの言う2つの恐怖を別々の箱に入れてはいない。彼らは両方を同時に管理し、国内と海外の圧力を同時に調整する首尾一貫したアプローチ、すなわち統治のための単一の戦略(single strategy for governing)を探し求めている。
レーガン主義(Reaganism)は、国内と国外を切り離すことができない単一のドクトリンであった。クリントン主義(Clintonism)もそうだった。トランプ主義(Trumpism)、プーティン主義(Putinism)、「習近平思想(Xi Jinping thought)」も同様だ。
従来の大戦略は、決して大戦略ではない。より大きなものの一面であり、統治するための全体的な戦略である。このことを認識し、大戦略の概念をそれなりに拡張している専門家もいる。ピーター・トルボウィッツは、大戦略を「国家指導者たちが行政権力を維持・強化しようとする手段」であり、単に外交政策上の目標を追求するための手段ではないと定義している。また、アンドリュー・モナハンは最近の著書で、大戦略を「国家の利益を促進するために国家のあらゆる資源を用いることであり、認識されている敵や現実の敵から国家を守ることも含まれる」と定義している。これらの定義は、国家戦略をより広く、より統合的に見るために、分析を一段階上に進めようとするものである。しかし、結局のところ、大戦略の研究は、国家安全保障と外交政策の問題に留まっているのが通常の姿だ。
これはある程度、学問的な便宜の問題だ。学界には、国内政策と外交政策を二分する長い伝統がある。しかし、このような概念的な区分は、指導者が実際に考える方法とは関係がない。リアリズムでは、統治のための戦略についてより広い視野が求められる。
より広範な視点を持つことには3つの利点がある。1990年代に予測された市場民主主義(market
democracy)が世界的に拡大し、それに収れんする(convergence)という予測は実現されていない。大国の統治戦略が再び大きく相違する時代に突入している。今後数十年間、競合する各国家戦略の利点をめぐる議論が展開されるであろう。20世紀初頭、1930年代、そして冷戦期、私たちはこれらの時代にそうした議論を経験している。どの国の改革者も、ライヴァル国のパフォーマンスに対する判断に影響を受けるだろう。その際、改革派は内政と外交を切り離して考えることはない。その際、改革派は内政と外交を分けて考えるのではなく、他国の実績を総合的に判断する。学者の役割は、このような世界的な議論を構成する手助けをすることである。私たちの理論的ツールキットが現実の会話を反映したものであれば、より効果的にこれを行うことができる。
国策に関する従来の常識が崩れた瞬間に、戦略を大きく把握することは有効だ。アメリカは今、このような瞬間に苦しんでいる。国内政策と外交政策についての古い共通理解(consensus)が崩れ、その断片を新しい構成に組み直すのに苦労している。国家政策の全体的なデザインについて話し合う必要がある。内政や外交の部分を切り離して考えるべきではない。そのためには、大戦略よりも大きな器が必要である。
広範な視野が持つ3つ目の利点は何だろうか?それは「真実性(Verisimilitude[ヴェリシミリチュード]、訳者註:英語ではtruthlikeliness)」だ。近代大戦略の父と呼ばれるマキャベリは、外交政策や内政の指針として『君主論』を書いたという訳ではない。この本は国家戦略全般の指南書(guide to statecraft in toto)だったのだ。しかし、現実主義者にとっては、この課題から逃れることはできない。指導者に区分けは許されないし、学者もそうであってはならない。
(貼り付け終わり)
(終わり)
※6月28日には、副島先生のウクライナ戦争に関する最新分析『プーチンを罠に嵌め、策略に陥れた英米ディープ・ステイトはウクライナ戦争を第3次世界大戦にする』が発売になります。
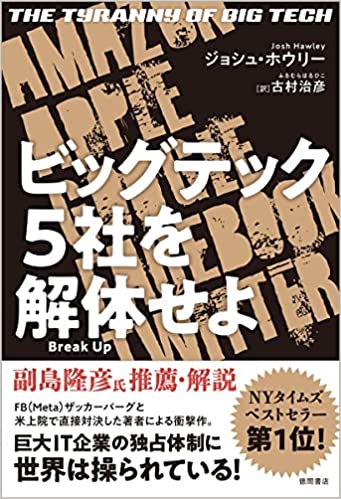
ビッグテック5社を解体せよ