古村治彦です。
日本列島はずっとアジア大陸の東の端という位置にありました。そして、アジア大陸の東端に存在した中華帝国からの影響を受け続けてきました。現在の中国、昔は各王朝の名前、漢、唐、宋などなどと呼ばれていた存在をどのように認識するか、敵か味方か、従うべき上位の存在か、対等な関係か、自分たちよりも弱い存在として見下すか、ということで、対岸の島国の人たちは迷って、様々な反応をしてきました。
現在、中国は日本を抜いて世界第2位の経済大国となりました。世界のGDPに占める割合はアメリカが23%、中国が15%、第3位の日本は5%ほどとなっています。20世紀末の段階ではまだ日本が中国をリードしていたのですから、中国の高度経済成長の凄まじさが分かります。最近でも年6%の経済成長で、だいぶ落ちてきたと言われていますが、世界第2位の規模の経済が6%ずつでも成長するというのは驚異的なことです。日本がこれから中国に追いついていくためには年で18%の成長を毎年続けていかねばなりませんが、そんなことは不可能です。
私自身に引きつけて考えてみれば、1984年、小学生の時に中国の上海を訪問したことがあります。地元新聞社の交流事業の一環で、子供たちばかりでの訪問でした。あの時は中国のあまりの貧しさに驚きました。おんぼろの上海空港、子供たちは日本の終戦直後かと思うほど皆白いランニングシャツに半ズボンばかり、私たちは普通の格好をしていたのですが、物珍し気に遠巻きにされて後ろをついてこられる、なんてことがありました。通訳の方からは子供たちがカメラを持っていることが珍しかったようです。クーラーもなくて大変でした。
上海のあるお寺で、壁が乱暴に削られた跡があり、通訳の方に「あれは何ですか?」と質問して、「文化大革命というのがあってね」と言われて、「文化大革命とは何ですか?」と質問したら、「日本に帰ってご両親から教えてもらって」と言われたことを記憶しています。あと興味深かったのは、私の耳は福耳なのですが、中国の人たちに何度か耳たぶを触られたこともありました。バスに乗っていたら、窓を叩かれ、開けてみたら、耳を触られたこともありました。しかし、何か乱暴をされるとか、嫌な目に遭うなんてことはありませんでした。
あの時、ランニングシャツを着て私たちの後をついてきた同い年くらいの子供たち、少年宮で体操競技の練習をしていた子供たちは今どうしているのだろうか、と考えると、上海でお金持ちになっているのかな、共産党の偉い人になっているのかな、と思うと、自分のふがいなさは置いておいて、中国の発展ぶりと日本の停滞ということを対比して考えてしまいます。
個人的な体験。ミクロの体験を基礎にして俯瞰的に、マクロに見るということが重要だと思いますが、これは簡単ではありません。話が逸れて申し訳ありません。
1800年当時、中国(清帝国)は世界のGDPの25%以上を占める世界最大の経済大国でした。割合で言えば現在のアメリカと同じくらいの規模です。そこから40年後のアヘン戦争で凋落して、屈辱の時代に入っていきます。世界覇権国(世界帝国)の歴史を見てみると、一度その座から滑り落ちたら復活したところはありませんが、中国は復活するという世界史において初めての偉業を成し遂げるかもしれません。
こうした大きな変化を目の当たりにして、私たちはどのように中国を認識すべきなのか、中国を認識するにはどうしたらよいのか、ということになります。「木を見て森を見ず」という言葉があります。自分の個人的な、狭い経験だけで判断してしまうことは正しい認識につなげることが出来ません。個人的な経験に政治、経済、社会、文化に関するこれまでの知識の蓄積を加えていくことが重要ですが、言うは易しで、これは大変難しいことです。日本の対中認識、対中姿勢は地理的にかつ文化的に近いために難しいものとなっています。
しかし、先穂との私のささやかな体験をつらつらと書いてしまったように、人間はどうしても個人的な体験を通してより大きなものを見てしまうということはあります。そうした呪縛を逃れるためには幅広い知識を得ることが重要だと思います。
今回は、坂野潤治著『近代日本とアジア』(ちくま学芸文庫、2013年)と戸部良一著『日本陸軍と中国 「支那通」にみる夢と蹉跌』(ちくま学芸文庫、2016年)を読みながら考えたことを書きたいと思います。私がこの2冊の良書を読んで感じたことは、外国を総体として「理解」することは不可能であり、「理解」したつもりになっていると痛い目に遭う、ということです。
『近代日本とアジア』では、日本の対アジア認識の近代史をテーマとしています。日本の対アジア(対中)認識は大きく分けると、「アジア主義」対「脱亜論」ということになります。雑駁な言い方になりますが、アジア主義と言えば頭山満が、脱亜論と言えば福沢諭吉がそれぞれ有名です。アジア主義は日本型のアジアの国々と一緒になって欧米諸国に対抗しようとする考えで、脱亜論は欧米諸国に倣ってアジア諸国に対して進出しようという考えです。明治期から大正期にかけて大きく分けてこの2つの考えが様々な形で主張されていきました。
「脱亜論」の代表格である福沢諭吉に関して言えば、福沢の主張は「朝鮮の日本による保護国化(ロシアと中国に備える)」というものでした。そして、福沢は「脱亜論」を唱えたのですが、時に「アジア主義」へと変化していきます。この変化は福沢の対中認識の変化に軌を一にしているのだと著者の坂野は主張しています。つまり、福沢が「中国は強い」と思った時には「脱亜論」を唱え、「中国は弱い」と考えた時には「アジア主義」を唱えたのですが、言いたいことは「だから朝鮮半島を日本の勢力下に置かねばならない」ということでした。朝鮮半島を日本の勢力圏に置いて、日本の安全保障を確保するということが明治日本の基本線でした。山縣有朋は朝鮮半島を含む地域を「主権線」、満州地域を「利益線」と呼び、これらを守ることの重要性を訴えました。
日本本土だけではなく、満州までも勢力圏(利益線)として防衛するという考えは、膨張し続けていくという宿命を負っています。満州を守るためにはモンゴルやシベリアの一部も勢力下にしなければならないということになって際限がなくなってしまいます。ですから、国家運営の基本方針がなければなりませんが、それがあったのかどうか、ということは疑問です。石橋湛山は戦前に既に朝鮮半島まで放棄し、独立させよという「小日本主義」を唱えていますが、このような慧眼はなかなか受容されませんでした。
現在、日本の置かれている状況を考えてみると、地理的条件はほぼ変わっていません。しかし、中国と韓国との関係、日本と韓国との関係、日本と中国との関係を考えてみると、中韓関係の緊密さに比べて、日韓、日中関係は疎遠のように見られます。日本は「孤立」し、ますますアメリカ依存を強め、膨張する中国に対抗するという状況にあります。簡単に言うと、日本は戦後70年を過ぎてもなお、アメリカの従属国として生きていかねばならないということです。そして、今世紀中に起きる覇権国交代により、中国がアメリカの次の覇権国になる時には、中国の従属国になるという運命にあるということです。米中どちらの従属国であるのがより良いのかということは分かりませんが、それが日本が置かれた場所から生み出される結論ということになるでしょう。ですから、このような事態に備えて、日韓、日中関係を少しでも改善しておかねばならないのですが、現在はまだアメリカの従属国であるということに徹しておかねばならないという状況です。
戸部良一著『日本陸軍と中国 「支那通」にみる夢と蹉跌』(ちくま学芸文庫、2016年)に移ります。
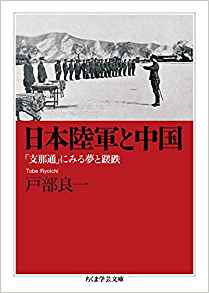
日本陸軍と中国: 「支那通」にみる夢と蹉跌 (ちくま学芸文庫)
この本の主人公的な人物は、佐々木到一(1886―1955年)です。1905年に陸軍士官学校を卒業し、連隊付きの将校となり、1911年に辛亥革命勃発後の中国に初めて入りました。この時から中国を専門とすることを志しました。1914年に陸軍大学に入学しました。陸軍大学では中国関係以外には熱心ではなく、何とか卒業できる成績だったそうです。それでも陸軍大学まで出れば、「閣下」と呼ばれる少将から上まで進級できました。陸大を出ていなければそこまでの出世は難しいものでした。
陸大卒業後は、途中で日本に帰ることもありましたが、長く中国に勤務しました。広東駐在武官、北京公使館付武官補佐官、南京駐在、関東軍、満州国軍政部最高顧問などを務めました。南京事件時には、南京攻略戦に旅団長として参加し、戦闘後には南京の警備司令官を務めました。戦後は戦犯として逮捕され、1955年に中国の戦犯収容所で死亡しました。
佐々木到一は、明治維新以降の中国に駐在した日本陸軍の士官たちである「支那通」の系譜につながる人物です。情報将校として中国の現地情報を収集・分析し、日本に伝える役割を果たしました。また同時に、中国の地方勢力や中央政府に深く食い込むことで、彼らの意向を日本に伝えるという役割も果たしました。
佐々木到一は1922年に広東駐在となり、ここで当時は広東を拠点としていた国民党政権を研究するようになりました。その過程で孫文と親しくなり、国民党による中国の統一と統治を期待するようになりました。孫文は1925年に亡くなりますので、交流期間は短かったのですが、孫文にも信頼されたということです。佐々木は孫文死後も国民党への期待を変えることはありませんでした。腐敗した各地の軍閥とは違い、三民主義を掲げた国民党による中国統一と清廉な統治を佐々木を期待しました。そして佐々木は蒋介石に期待をかけることになりました。
1928年、中国国民党が主導する国民革命軍による北伐が開始されると、佐々木は蒋介石の許可を得て北伐に従軍しました、しかし、1928年5月に済南で国民革命軍と日本軍が衝突する事件が起きました。この時、佐々木は停戦の仲介に向かう途中に国民革命軍の兵士に捕らえられ、厳しいリンチを受けてしまいました。これ以降、佐々木と中国側、国民党側の関係は冷却し、破綻してしまいます。そして、佐々木は国民党への期待から一転して、中国に対して厳しい態度を取ることになりました。それは日中戦争が始まっても続くことになりました。
佐々木到一は辛亥革命で革命の熱気にあてられ、孫文に出会い、その理想に共鳴しました。しかし、孫文の死後、その理想が裏切られる事件に遭遇し、今度は厳しい批判者となりました。佐々木はその生涯の中で、中国の友人から批判者へと大きく変化した訳ですが、これは日本に対中姿勢とその変化を自身の中で経験したということが言えます。
佐々木のようにロマンティシズムと理想主義で中国をとらえてしまうと、それらが裏切られてしまえば、勝手に失望し、幻滅して、中国を批判し、悪口を言い出すということになります。私たちは、このようなある面では子供じみた態度を取るべきではありません。この点で、佐々木到一という人物は私たちに教訓を教え得てくれています。
中国は昔も今も日本に影響を与える国です。敵視してみたり、従ってみたり、友人だと言ってみたり、様々な反応をしてきました。一衣帯水、同文同種とも言ってきました。期待をしたり、裏切られたと言って憤ってみたりということもありました。中国は再び世界帝国への道を進み始めています。その道は直線ではないかもしれませんが、既に日本の3倍のGDPというところまで来ました。この現実を受け止め、どのように行動することが日本にとって最良なのかということを国民全体で考える必要があると思います。ただただ怯えて過剰な反応をするだけでは未来につながりません。
(終わり)
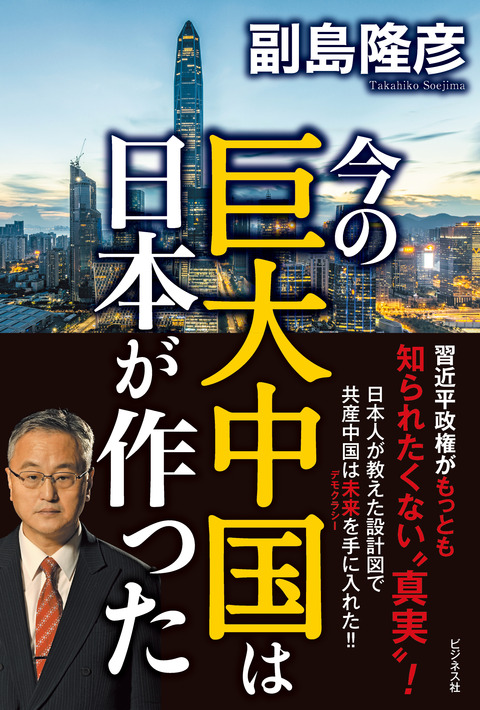
今の巨大中国は日本が作った







